韓国旅行でごはんを食べると、メイン料理の前にたくさんの小皿がずらりと並んでいるのに驚いたことはありませんか?
このおかず文化、韓国語では「반찬(パンチャン)」といって、単なる添え物ではなく、料理の主役といってもいいほど大切な存在なんです。
でも、なぜこんなにもおかずが多いのでしょう?
今回は、そんな韓国のおかず文化の背景をご紹介します。
知れば知るほど「なるほど!」が詰まった、知恵と優しさのつまったパンチャンの世界を、一緒にのぞいてみましょう!
韓国のおかず文化のはじまりは「暮らしの知恵」から

日本には『一汁三菜』という言葉がありますが、韓国には昔から、『一汁多菜(イルチュッタチャイ)』という食文化が根付いていて、ご飯と汁物、そして複数のおかずを揃えるのが基本とされてきました。
おかずをたくさん用意するのは大変だと思うのですが、なぜこのような文化が発展したのでしょうか。
実は、韓国料理におかずが多くなった背景には、韓国の歴史と暮らしに根ざした知恵があるんです。
- 仏教文化の影響
- 保存の工夫としての発酵文化
- 宮廷料理の影響
こうした背景から、「いろんな種類を少しずつ」「目でも楽しめる」「栄養バランスを考える」スタイルが自然と定着しました。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう!
仏教文化の影響
三国時代から高麗時代にかけて、仏教が国教とされていた韓国では、動物性食品の摂取が制限されていました。
その結果、豆腐や野菜、山菜、海藻類などを中心とした菜食文化が発達し、バラエティ豊かなおかずが発展しました。
特に韓国の仏教料理は「五味(甘・辛・酸・苦・塩)」の調和を大切にし、心身のバランスを整えることを目的とした「食の修行」としての側面を持っています。
たとえば「韓定食」に見られるような色とりどりの小鉢や、あっさりとした味付け、季節の野菜を使う工夫などは、こうした仏教文化の延長線上にあります。
寺院での食事(사찰음식/サチャルウムシク)では、にんにくやネギ、ニラといった刺激の強い食材も避けられており、素材の味を活かす調理法が発展しました。
こうして生まれた「シンプルだけど深みのあるおかず」は、時代が変わっても家庭の味として生き続け、現代のパンチャンの原型をつくったのです。
保存の工夫としての発酵文化
四季が明確な朝鮮半島では、特に冬の備えとして保存食づくりが欠かせませんでした。
冷蔵庫のない時代、食材を長く保存するための工夫として「塩漬け」や「発酵」の技術が自然と発展。
これが、キムチをはじめとする発酵系パンチャンのバリエーションを生み出すきっかけとなりました。
一度にたくさん作って常備できるこれらの食品は、食卓に欠かせない存在として定着しました。
また発酵食品は保存がきくだけでなく、時間が経つごとに味がまろやかになったり、酸味が出たりと、日を追って楽しめるのも魅力。大量につくって小皿にちょこちょこ出せば、忙しい日の食卓がぐんと豊かになります。
キムチだけでも、白菜、大根、きゅうり、ネギなど種類は無数。家庭ごとに味が異なり、まさに「おかず=家の個性」という文化を形づくっていきます。さらに、テンジャン(味噌)、コチュジャン(唐辛子味噌)、醤油などの発酵調味料が揃うことで、パンチャンの味つけはより奥深いものとなりました。
キムチや塩辛、ナムルなどは、冷涼な気候のなかで生まれた「保存の知恵」。
「限られた食材を、長く・おいしく・安全に」食べるための知恵こそが、現代のパンチャン文化の基礎を築いたのです。
宮廷料理の影響
朝鮮王朝時代、王族や貴族が食べていた「宮廷料理(궁중요리)」は、韓国料理の「見た目」と「格式」を重んじるスタイルに大きな影響を与えました。
なかでも有名なのが「12品のパンチャン」で構成される豪華な宮廷料理。
王の食卓である「수라상(スラサン)」には、12種類以上の料理が並びました。その内容は前菜、焼き物、煮物、蒸し物、和え物、汁物、デザートと多岐に渡り、一品一品に高度な調理技術と美意識が求められたのです。
その際に重視されたのが「五味五色(오미오색)」の概念。味のバランス(甘・辛・酸・苦・塩)と色彩の調和(赤・青・黄・白・黒)を整えることで、見た目にも鮮やかで、体にも優しい食事が完成するという考え方です。
この宮廷料理の影響が庶民の間にも広まり、祭祀(チェサ)や年中行事の料理として浸透したことで「彩りよく、たくさんの種類を少しずつ」という現代のパンチャンスタイルの原型になっていきました。
特に「並べ方」「見せ方」へのこだわりは、現代の家庭料理にも生きていて、たとえシンプルなおかずでも、丁寧に小皿に盛り付けることで心を込めた一食になる。そんな「おもてなしの精神」も、パンチャン文化の魅力のひとつです。
パンチャンがただの副菜ではなく、韓国の美学と生活文化が詰まった存在である理由は、まさにこの宮廷料理の精神からきているのかもしれません。
現代のパンチャン事情〜変わらない文化と、変わってきた暮らし〜

時代が進んだ今の韓国でも、パンチャン文化は健在です。
ただし、ライフスタイルの変化によって、そのあり方は少しずつ変化しています。
近年では、共働き家庭が増えたことや核家族化の影響で、毎日たくさんのおかずを手作りするのは難しいという家庭も多くなりました。
そんななかで進化してきたのが、市販のお惣菜文化です。
スーパーや市場、コンビニにはキムチやナムル、チャプチェなどのパンチャンがずらり。「今日はこの中から3つ選ぼう〜」と、気軽に組み合わせて楽しむスタイルが定着しています。
また、環境への配慮や食品ロスへの意識の高まりから、小分けパックや量り売りのパンチャンも人気です。
食卓に並ぶ小皿たちは、伝統を大切にしつつ、今の暮らしに寄り添って形を変えています。パンチャンは、まさに韓国の「食の今」を映し出す鏡のような存在なのです。
ちなみに、韓国の飲食店ではパンチャンは無料でついてくるうえにおかわり自由なことも多く、旅行者には驚きの「太っ腹文化」として印象に残ります。
「パンチャンだけでお腹いっぱいになりそう!」と思ってしまうほど。
日常の中にある「ちょっとしたごちそう」が、韓国のごはん時間をより豊かなものにしているのかもしれませんね。
知ればもっと美味しい!おすすめパンチャンたち
最後に、韓国のおかず(パンチャン)の中でも、「これは覚えておきたい!」という定番&人気メニューをいくつかご紹介します。
どれも日本の家庭でも作りやすいので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてくださいね!
🥗 ナムル(나물)
茹でた野菜にごま油や塩、にんにくで味付けしたシンプルなおかず。
ほうれん草やもやし、大根などいろんな野菜で作れるうえ、ビビンバにも使える万能選手!
🥚 ジョン(전)
チヂミに似た料理で、野菜や魚、肉に衣をつけて焼いたもの。
日本の「おかず兼おつまみ」にもぴったり。お弁当にも◎!
🥢 キムチ(김치)
発酵食品の代表格。熟成度によって味が変わるのも魅力。
キムチチゲやチャーハンなど、いろんな料理に使えて便利です。
このあたりのレシピや活用方法は、今後の別記事でたっぷりご紹介する予定です♪
「どれから作ろう?」と迷った方は、まずはもやしのナムルからどうぞ。簡単&失敗しにくいです✨
まとめ:韓国のおかず文化は、知恵と優しさのかたまり
韓国のパンチャン文化には、歴史・暮らしの知恵・おもてなしの心がギュッと詰まっています。
たくさんの種類を少しずつ並べるのは、「飽きずに、美味しく、体に優しく」食べてもらうための工夫。
それは、毎日の食卓をちょっと特別にしてくれる魔法かもしれません。
これからも、そんな韓国の「食の知恵」を、楽しくお届けしていきたいと思います!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

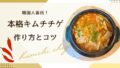

コメント